日誌
下関河内小だより
ホウシャセンってなあに? 放射線学習
京都大学大学院エネルギー科学研究科 幸 浩子 先生を講師にお招きし、全校児童で放射線について勉強しました。
東京電力福島第一原子力発電所の事故から、まもなく4年が経過しようとしています。
幸いに当地は、事故後も放射線量はそう変わらない状況(本校のモニタリングポストの数値は、0.08~0.09μSv/h程度で推移)で、除染作業も必要なく、事故後も運動会はこれまで通り校庭で実施しているなど、ほぼ通常通り教育活動を実施しております。しかし、事故があった原子力発電所では未だに廃炉に向けた工程は厳しい状況です。また、除染もかなり進んできているとはいえ、環境中に放出された放射性物質の影響が続いている地域も少なくありません。子どもたちに放射線についての正しい知識を身につけさせることは、本校においても喫緊の課題であると考えています。
あのような事故は、二度と再び起こしてはなりませんが、この狭い国土に50基以上もの原子力発電所を抱える我が国に於いて、絶対に起こらないという保証はどこにもありません。大人たちが築いたこのような状況を子どもたちに引き継ぐからには、せめて正しい知識を身につけさせるのは私たち大人の責任です。人間の英知をどんなに集めても自然災害を起こさないようにすることは不可能ですが、ヒューマンエラーを起こさない社会システムを構築することは可能だと思うのです。子どもたちが築く明日の社会がそのような社会になってほしいと願ってやみません。
 霧箱で放射線の飛跡を観察する様子
霧箱で放射線の飛跡を観察する様子
東京電力福島第一原子力発電所の事故から、まもなく4年が経過しようとしています。
幸いに当地は、事故後も放射線量はそう変わらない状況(本校のモニタリングポストの数値は、0.08~0.09μSv/h程度で推移)で、除染作業も必要なく、事故後も運動会はこれまで通り校庭で実施しているなど、ほぼ通常通り教育活動を実施しております。しかし、事故があった原子力発電所では未だに廃炉に向けた工程は厳しい状況です。また、除染もかなり進んできているとはいえ、環境中に放出された放射性物質の影響が続いている地域も少なくありません。子どもたちに放射線についての正しい知識を身につけさせることは、本校においても喫緊の課題であると考えています。
あのような事故は、二度と再び起こしてはなりませんが、この狭い国土に50基以上もの原子力発電所を抱える我が国に於いて、絶対に起こらないという保証はどこにもありません。大人たちが築いたこのような状況を子どもたちに引き継ぐからには、せめて正しい知識を身につけさせるのは私たち大人の責任です。人間の英知をどんなに集めても自然災害を起こさないようにすることは不可能ですが、ヒューマンエラーを起こさない社会システムを構築することは可能だと思うのです。子どもたちが築く明日の社会がそのような社会になってほしいと願ってやみません。
 霧箱で放射線の飛跡を観察する様子
霧箱で放射線の飛跡を観察する様子 子どもの運動の今昔
全国的に子どもの体力・運動能力の低下が懸念されています。本校でも、走力や投力などに課題が見られます。
投力とは、文字通り投げる力ですが、投力の低下は、子どもの遊びや運動の変化が起因しているものと思われます。かつては、水切りや雪合戦など投げて遊ぶことが多く、また、運動と言えばなんといっても野球(男の子の場合ですが)でした。友だちや父親とキャッチボールをしたり、相手がいない場合は一人で「壁投げ」をして遊んでいる光景をよく見かけたものです。今では、運動の好みも多様化し、サッカーやテニスなどに人気が移ってしまい、キャッチボールをして遊ぶ光景はまず見られなくなりました。(もちろん中学とかの野球部の子は別ですが・・)
今、学校では、どのようにして投力を高めようとしているかというと、体育の授業で「運動身体づくりプログラム」(福島県教委が制作した運動メニュー)というのを行っています。その中で「投運動」といって、端っこを縛ったタオルを投げる運動があります。


上の写真が、その様子です。
タオルを遠くに飛ばすには、うでだけではなく全身のバネを上手に使う必要がありますが、特に重要なのは「左手」のふりです。右ききの場合、まず、①左足を大きく踏み出すと同時に左手も大きく前につきだし、②そして右足を思い切り蹴ると同時に左手を勢いよくふり戻し、③右手で投げるのですが、そうすると投げ終わった時は、左手は体のうしろにまわり右足が前にでているはずです。
ところが、左の写真を見てください。左手が全く使われておらず、右足の蹴りも十分ではありません。従って、右の写真のように、投げ終わった後、左手が体の前にあって、右足も後ろに残ったままになってしまうのです。こうした課題を今後の指導で改善していけば、投力も向上すると考えています。
かつては、放課後や休日の遊びや運動で自然と身につけていたことでも、今は学校の授業で教えなければならない(投力に限ったことではありませんが・・・)、子どもの遊びの今昔を感じています。
ゲームやテレビではなく、外遊びで、体力と知恵を身につけてほしいものです。
投力とは、文字通り投げる力ですが、投力の低下は、子どもの遊びや運動の変化が起因しているものと思われます。かつては、水切りや雪合戦など投げて遊ぶことが多く、また、運動と言えばなんといっても野球(男の子の場合ですが)でした。友だちや父親とキャッチボールをしたり、相手がいない場合は一人で「壁投げ」をして遊んでいる光景をよく見かけたものです。今では、運動の好みも多様化し、サッカーやテニスなどに人気が移ってしまい、キャッチボールをして遊ぶ光景はまず見られなくなりました。(もちろん中学とかの野球部の子は別ですが・・)
今、学校では、どのようにして投力を高めようとしているかというと、体育の授業で「運動身体づくりプログラム」(福島県教委が制作した運動メニュー)というのを行っています。その中で「投運動」といって、端っこを縛ったタオルを投げる運動があります。


上の写真が、その様子です。
タオルを遠くに飛ばすには、うでだけではなく全身のバネを上手に使う必要がありますが、特に重要なのは「左手」のふりです。右ききの場合、まず、①左足を大きく踏み出すと同時に左手も大きく前につきだし、②そして右足を思い切り蹴ると同時に左手を勢いよくふり戻し、③右手で投げるのですが、そうすると投げ終わった時は、左手は体のうしろにまわり右足が前にでているはずです。
ところが、左の写真を見てください。左手が全く使われておらず、右足の蹴りも十分ではありません。従って、右の写真のように、投げ終わった後、左手が体の前にあって、右足も後ろに残ったままになってしまうのです。こうした課題を今後の指導で改善していけば、投力も向上すると考えています。
かつては、放課後や休日の遊びや運動で自然と身につけていたことでも、今は学校の授業で教えなければならない(投力に限ったことではありませんが・・・)、子どもの遊びの今昔を感じています。
ゲームやテレビではなく、外遊びで、体力と知恵を身につけてほしいものです。
インフルエンザの防止のために
インフルエンザの流行期となりました。ご家族に受験生がおられるご家庭では特に心配な時期ですね。近隣の小学校で流行始めたという情報もあり、本校でも、十分気をつけて、うがい・手洗いの指導、教室の換気や清浄などに努めて参ります。ご家庭でも、帰った時や食事の前には、うがい・手洗いをご指導いただくと共に、人が集まる場所に出かける際にはマスクの着用などの対応をお願いいたします。(できれば、そのような場所には、なるべく行かせないのが一番ですが、・・・) また、もし急な発熱などインフルエンザ様症状が現れた場合には、医療機関に受診させていただくようお願いいたします。
なお、インフルエンザと診断された場合は「出席停止扱い」(この場合、出席簿では欠席とはならず、出席を要しない日として扱われます)となりますので、学校にもご一報ください。出席停止の期間等、詳しくは保健だよりをご覧ください。
子どもたちが、元気に登校し、思う存分学べるよう、ご家庭と協力しながら、この時期を乗り越えていきたいと思います。
なお、インフルエンザと診断された場合は「出席停止扱い」(この場合、出席簿では欠席とはならず、出席を要しない日として扱われます)となりますので、学校にもご一報ください。出席停止の期間等、詳しくは保健だよりをご覧ください。
子どもたちが、元気に登校し、思う存分学べるよう、ご家庭と協力しながら、この時期を乗り越えていきたいと思います。
新年の思いを込めて~校内書き初め大会
明けましておめでとうございます。
第3学期のはじめに、児童一人一人が新年の抱負を思い思いの文字に込めて書く、校内書き初め大会を行いました。1・2年生は硬筆、3年生以上は毛筆での挑戦です。昨年、片野先生からいただいたご指導を思い出しながら、姿勢を整え、心を整えて、一心不乱に紙に向かいました。
どの子も、その思いを達成できるよう、教職員一同、三学期も親心で指導して参ります。
本年もよろしくお願いいたします。






心を整える~書き初め練習
片野先生にご指導いただき、書き初めの練習を行いました。
まず、お手本をかいていただき、お手本をもとに筆をおろす位置や筆の運び方などを説明していただき、練習では一人一人にアドバイスをいただきました。
「筆を下ろしたら、しっかり止める、さあ、息を止めて・・・そこをぐっと、そう、そこでまた筆をしっかり止めて・・・そう、そう、・・・上手になったね。」
まさに、「やって見せ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば人は動かじ」という片野先生のご指導は、私たち教師にとってもお手本となりました。
片野先生のご指導で、子どもたちのうでもみるみる上達しました。そして、書を整えるには、姿勢を整え、心を整えなければならないことを、子どもたちも学んでくれたと思います。
これで、よい新年が迎えられそうです。






まず、お手本をかいていただき、お手本をもとに筆をおろす位置や筆の運び方などを説明していただき、練習では一人一人にアドバイスをいただきました。
「筆を下ろしたら、しっかり止める、さあ、息を止めて・・・そこをぐっと、そう、そこでまた筆をしっかり止めて・・・そう、そう、・・・上手になったね。」
まさに、「やって見せ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば人は動かじ」という片野先生のご指導は、私たち教師にとってもお手本となりました。
片野先生のご指導で、子どもたちのうでもみるみる上達しました。そして、書を整えるには、姿勢を整え、心を整えなければならないことを、子どもたちも学んでくれたと思います。
これで、よい新年が迎えられそうです。






達人から学ぶ~くぎ打ち体験学習
3・4年生の図画工作の時間に、永山先生に「くぎ打ち」のご指導をいただきました。
色々な種類の釘をみせていただき、また、とても大きなトンカチで杭を打つ体験をさせていただきました。その道の「達人の技」を子どもたちは目を輝かせて見ていました。こうした憧れも子どもたちの成長の大きな糧となると思います。永山先生ありがとうございました。


色々な種類の釘をみせていただき、また、とても大きなトンカチで杭を打つ体験をさせていただきました。その道の「達人の技」を子どもたちは目を輝かせて見ていました。こうした憧れも子どもたちの成長の大きな糧となると思います。永山先生ありがとうございました。


森林を育てよう~どんぐりの種まき
全国植樹祭の記念事業の一環として、どんぐり(ミズナラ、クヌギ)の種まきを行いました。
木を育てるためには、木を上手に活用することも大切であることを学びました。矢祭町の豊かな自然を子どもたちに引き継がせていきたいと思います。

木を育てるためには、木を上手に活用することも大切であることを学びました。矢祭町の豊かな自然を子どもたちに引き継がせていきたいと思います。

子どもに充実した読書体験を!~もったいない図書館活用のすすめ~
読書には様々なスタイルがありますが、小学生は、よい本に出会ったら、くり返し何度も読んでほしいと願っています。子どもへの読書のすすめも方も、「何冊以上読みましょう」というのも確かにひとつの方法ですが、読書は、量ばかりでなく質も大事なのではないかと思うのです。例えば、ある子どもが、クリスマスのプレゼントにピッカピカの絵本を買ってもらって、くり返し何回も何十回も読んで、ストーリーやセリフを全部おぼえて、その物語で兄弟姉妹で「ごっこ遊び」をしたり、自分の物語をつくったり、物語にあわせて絵を描いたりしたとします。その子が冬休みに読んだ本は、その本たった1冊ですが、とても価値ある読書体験だと思うのです。「手づくり絵本」もそうした深い充実した読書体験の延長にあるのでしょう。小学生には、そうした読書体験をさせたいものです。「たくさんの本を読む」のはもう少し大人になってからでも間に合います。私自身も、一週間に何冊も本を読むようになったのは、高校生になって文庫本や新書本を読むようになってからで、小学生の頃は、プレゼントに買ってもらった「ドリトル先生」の物語を、何度も何度も読み返したことをおぼえています。(小学生が読む物語本は机上版なので値段も高く、そうは買ってもらえない。文庫本は安いので高校生の小遣いでも買えるというのも理由のひとつかも知れませんが・・・。)
しかしそれには、子どもがくり返し何度も読める、深く充実した読書体験に耐えうるだけの良書が必要です。(残念ながら今時流行の「ケイタイ小説」などでは、そのような深い読書体験はできないと思います。)
良書を、子どもの身近に整えてあげるのは、私たち大人の責任です。今日、手のひらの会の方に読み聞かせをしていただいた「葉っぱのフレディ」などもそういう良書のひとつであると思います。(葉っぱのフレディや星の王子様などは、大人になってからもくり返し読みたい本です。30代や50代で読むと、また違った味わいがあります。)
そして、矢祭町には「もったいない図書館」というすばらしい図書館があり、そこには良書がずらりと並んでいます。これを活用しない手はありません。
この冬休み、子どもたちがよい本と出会い、充実した読書体験ができるよう、ご家庭でもご協力をお願いいたします。
しかしそれには、子どもがくり返し何度も読める、深く充実した読書体験に耐えうるだけの良書が必要です。(残念ながら今時流行の「ケイタイ小説」などでは、そのような深い読書体験はできないと思います。)
良書を、子どもの身近に整えてあげるのは、私たち大人の責任です。今日、手のひらの会の方に読み聞かせをしていただいた「葉っぱのフレディ」などもそういう良書のひとつであると思います。(葉っぱのフレディや星の王子様などは、大人になってからもくり返し読みたい本です。30代や50代で読むと、また違った味わいがあります。)
そして、矢祭町には「もったいない図書館」というすばらしい図書館があり、そこには良書がずらりと並んでいます。これを活用しない手はありません。
この冬休み、子どもたちがよい本と出会い、充実した読書体験ができるよう、ご家庭でもご協力をお願いいたします。
読書感想文発表会その2
2回目となる読書感想文発表会を行いました。今日紹介された本は、「どこか行きのバス」「ともだちはサティー」「おっちゃんの長い夏休み」の3冊です。発表に対しての感想もたくさん寄せられました。
土日や冬休みには、ぜひご家族で一緒に本を読んだり、思い出に残る本を紹介しあったりしてみてはいかがでしょう。
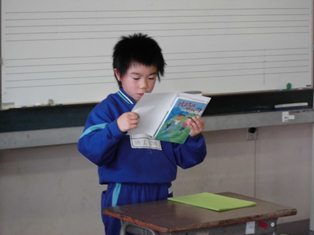
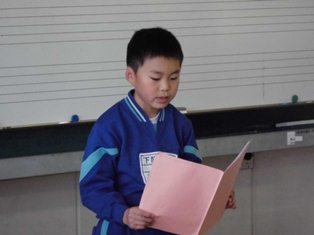

土日や冬休みには、ぜひご家族で一緒に本を読んだり、思い出に残る本を紹介しあったりしてみてはいかがでしょう。
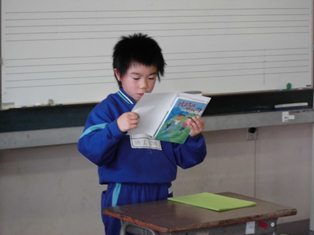
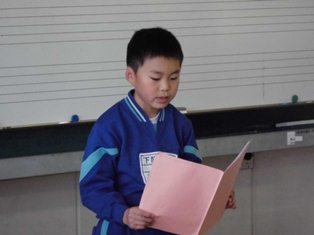

今年最後の読み聞かせボランティア
手のひらの会の皆様による今年最後の読み聞かせが行われました。今日読んでいただいた本は、低学年が「シチューをもらったかえりみち」(第1回矢祭町手づくり絵本コンクールの最優秀作品)、中学年が「葉っぱのフレディ」、高学年が「アンジェリーナのクリスマス」です。よい本に出会うことは人生をとても豊かにしてくれます。手のひらの会の皆様、大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。






QRコード
アクセスカウンター
2
0
6
9
1
6

